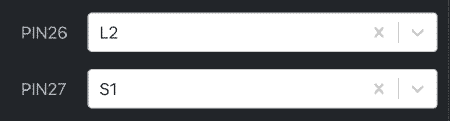<1> リック・デッカード
「ムード・オルガン」にセットされた気分で目覚めるリック・デッカードと妻のイーラン。
最終世界大戦後に放射性降下物に覆われてしまったこの地球では、生きた動物を飼うことが人間のステータス になっている。
リックは屋上で飼っている羊が本物でないことが皆にバレることを恐れている。
動物を飼わない人間は不道徳で同情心がないと思われるらしい。
死の灰の効果は薄れつつあったが、少しずつ人間の精神を蝕んでおり、毎月の身体検査で 適格者(レギュラー) と 特殊者(スペシャル) に分けられる。
適格者は植民惑星への移住や生殖が許可されるが、特殊者は頭がやられてしまい退化したものとみなされ、地球から抜け出すことができない。
リックは植民惑星から地球に逃れてくる脱走アンドロイドを処理するバウンティ・ハンターで、ひと月に4人のアンドロイドをしとめた実績がある。
リック自身は今のところ適格者(レギュラー)だが、この仕事のため地球に残っている。
リックは屋上の電気羊に嘆きつつ、ホバー・カーに乗って仕事へ出かける。
<2> J・R・イジドア
最終世界大戦後の地球は、今や太陽すら仰ぎ見ることができないほど汚染されてしまった。
植民惑星へ移住する人間には、国連法によって下僕となるアンドロイド一体を無料貸与されることになっている。
こんな地球の、特に郊外に居座っている人間は、特殊者(スペシャル)であることが多い。
世間では特殊者のことを侮蔑的に「マル特」と呼んでいる。
ジョン・イジドア も 1 年前に特殊者と判定されてしまった一人であり、さらに、精神機能テストにもパスできず、頭のおかしくなってしまった「ピンボケ」の仲間入りである。
イジドアは、崩れかかった巨大なビルに一人で住んでいる。
部屋に置かれた「共感ボックス」の取手を両手で握ると、視覚像が凝結した。
イジドアは マーサー教 の ウィルバー・マーサー と一体化し、彼とともに山を登っているような感覚に陥った。
そこでは同じように共感ボックスを使っている人々と感情を共有することができ、石をぶつけられると痛みさえ伝わってくる。
イジドアは共感ボックスを通じてマーサー教の教えを学び、特殊者(スペシャル)であっても心の清らかな者は救われると信じている。
共感ボックスから離れると、自分しか住んでいないはずビルの中で、テレビの音が聞こえた。
これはうちのテレビじゃない。
もうひとりぼっちじゃない!
<3> デイヴ・ホールデン
リックは司法本部に出勤した。
そこで上司のハリィ・ブライアント警視に、主任バウンティ・ハンターのデイヴ・ホールデンが撃たれたことを知らされる。
秘書のアン・マーステンは、最新のネクサス6型脳ユニットを備えた高知能アンドロイドだ。
ネクサス6型アンドロイドの親工場は火星にある。
1989年にズーデルマン社のT14型が出たとき、探知方法がなく50人が地球に逃げ込んでしまったが、今では感情移入度測定検査「フォークト・カンプフ検査」で見分けられるとされている。
最新のネクサス6型は知能に関しては特殊者(スペシャル)を凌いでおり、どんな知能テストもクリアしてしまうが、フォークト・カンプフ検査なら有効かもしれない。
リック・デッカードは、人間型ロボットは「独居性の捕食者」だと考えており、マーサー教には逃亡したアンドロイドを殺せと教えられているため、アンドロイドを廃棄処理することに躊躇はない。
<4> マックス・ポロコフ
ブライアント警視によると、アンドロイドに撃たれたデイヴは、8体の脱走アンドロイドの内すでに2体を片付けたらしい。
リックはデイヴの代わりに主任バウンティ・ハンターを務めたいと申し出る。
デイヴを出し抜いたのは、「マックス・ポロコフ」という名前のネクサス6型アンドロイドだった。
リックは、フォークト・カンプフ検査がネクサス6型にも有効かどうかを試すため、シアトルのローゼン教会に向かう。
ネクサス6型を開発した大手のアンドロイド生産会社だ。
ちなみに、フォークト・カンプフ検査は繊細な検査のため、人間の精神病患者も合格できない可能性がある。
ローゼン社に着くと、エルドン・ローゼン社長の娘だというレイチェル・ローゼンが出迎えた。
エルドン・ローゼン社長が最初の被験者に選んだのは娘のレイチェルだった。
<5> レイチェル・ローゼン
リックはレイチェルにフォークト・カンプフ検査を実施してアンドロイドだと判断したが、彼女は人間だったようだ。
エルドン・ローゼン社長は、彼女が特殊な環境(宇宙船の中)で育ったため、感情移入能力が非常に低いのだと説明した。
いきなり検査に失敗してしまったため、リックは続きの検査は行わないことにした。
この検査に基づいてアンドロイド狩りに出かけていたら大変なことになっていた。
レイチェルは、リックが脱走アンドロイドを捕まえてくれるのであれば、本物のフクロウを差し上げると言った(この世界では生きたフクロウは非常に高価)。
このとき、リックはレイチェルがフクロウのことを彼女 (her) と呼ばずに、それ (it) と呼んだことに違和感を覚え、もう一度検査を行うことにした。
とある残酷な質問で計器の指針が狂ったように振れたが、その前に一瞬の間があったとことをリックは見逃さなかった(ネクサス6型は14種類の基本的反応態度を持つが、切り替えに0.45秒かかるとされている)。
レイチェルはここで初めて自分がアンドロイドだということを認識する。
レイチェルは精巧なアンドロイド、ネクサス6型だったのだ。
カンプフ検査は今でも有効だ。
<6> プリス・ストラットン
ジョン・イジドアがテレビの音のする部屋をノックすると、音がばったりと途絶えた。
若くて美しい女がいた。
テレビの有名なコメディアン「バスター・フレンドリー」の話を振ってみたが彼女は知らないようだ。
なぜ知らないのだろう?
共感ボックスによる「ウィルバー・マーサーの山登り」の話も振ってみた。「きみは融合に加わらないの?」「なぜ共感ボックスを持っていないの?」
何か話が噛み合わないが、イジドアは自分がピンボケだからなのだと思った。
イジドアは口をすべらせて自分が知能テストにパスできなかった特殊者(スペシャル)であることがバレてしまう。
イジドアが去ろうとするとき、彼女は言った「わたしの名はレイチェル・ローゼン」。
イジドアがローゼン教会のことを切り出すと、彼女は「プリス・ストラットン」だと名乗り直した。
<7> ヴァン・ネス動物病院
イジドアはヴァン・ネス動物病院(実際は模造動物の修理店)で働いており、客から預かった病気の電気猫を病院へ運ぼうとしていた。
イジドアはテレビのバスター・フレンドリー・ショーが好きだったが、ときどきバスターが共感ボックスのことをからかうのが気に食わなかった。
なぜバスターはいつもマーサー教を冗談のネタにするのだろう?
きっと妬んでいるんだ。競争相手なんだ。何の?
バスターやその出演者はなぜ四六時中放送を続けられるのだろう?
ヴァン・ネス動物病院のハンニバル・スロートは特殊者(スペシャル)ではないが、移住には年を食いすぎていた。
死の灰が彼の顔と思考を灰色に変えてしまった。
イジドアは雇ってくれたスロートに感謝していたし、よき相談相手でもあった。
イジドアが預かった猫は本物の猫で、運んでいる間に死んでしまった。
イジドアは模造だと思い込んでいて、猫に付いたスイッチを探したりしていた。
イジドアは自分がまともに会話をできないことは分かっていたが、飼い主に電話(この世界では映話)しなければいけない。
映話が繋がると依頼主の妻(ピルゼン婦人)が出て、やはり最初はまともに喋れなかったが、急に流暢に話せるようになった。
イジドアはそっくりの模造猫を飼うことを提案し、彼女はそれを受け入れた。
夫には秘密のまま模造猫を試してみることにした。
<8> リック vs ポロコフ
ハリィ・ブライアント警視によると、同僚のデイヴを撃った脱走アンドロイドのポロコフは、特殊者を装ってベイ・エリアの清掃公社で働いているようだ。
リックは清掃公社のオフィスに出向いたが、ポロコフは無断欠勤していた。
すぐにポロコフの自宅を訪ねたがもぬけのからだった。
デイヴをレーザー銃で撃ったあとにすぐに逃げたのだろう。
レイチェル・ローゼンから映話がかかってきて、脱走アンドロイドの処理に協力すると提案してきたが、リックはローゼン一族にかかわりたくなかったので断った。
世界警察機構 (WPO) のデカで「サンドール・カダリィ」と名乗るものが協力のために合流してきたが、それがポロコフだった。
リックは首を掴まれたが、間一髪で仕留めることができた。
<9> ルーバ・ラフト、クラムズ巡査
リックは次のアンドロイド「ルーバ・ラフト」を処理するためにオペラ劇場へ向かい、楽屋を訪れた。
ルーバ・ラフトは、リック自身が先に検査を受けるなら自分も検査を受けると言うが、リックは検査には経験が必要だといって検査を強行した。
セクハラとも取れる質問を受けたルーバ・ラフトはリックのことを不審者だと思い、レーザー銃を向けて警察を呼んだ。
アンドロイドであればなぜすぐに撃たずにそんなことをするのかとリックは考えた。
きっと彼女は自分自身のことを人間だと思い込んでいるんだ。
クラムズ巡査と名乗る警官が現れたが、リックのことも上司のハリィ・ブライアント警視のことも知らないと言う。
リックはこの男もアンドロイドなのだと直感した。
リックはブライアント警視に映話をかけクラムズ巡査と代わったが、なぜかそこには誰も映っていなかった。
きっと映話の故障だろう。
クラムズ巡査はリックを司法本部へ連行しようとし、リックもけりをつけたいので素直に従うことにした。
おかしい、クラムズ巡査は間違った方向へ飛んでいる。
リックは全てを理解した。
おれもこれでおしまいだ。
<10> ガーランド警視、フィル・レッシュ
一度も見たことのないミッション通りの司法本部に連れてこられたリックはテストにかけられる。
さっぱりわからない。
この警察機関は我々(サンフランシスコ司法本部)のことを把握しておらず、我々もこの警察のことを知らなかった。
リックは自宅へ映話をかけてみたが、見知らぬ女性が出るだけだった。
ガーランド警視が現れ、リックを自分の部屋に連れて行く。
リックのカバンに入っていた処理命令リストには、ポロコフ、ミス・ラフト、……その次にガーランド警視の名前があった。
ガーランドは所属のバウンティ・ハンターであるフィル・レッシュを呼ぶ。
彼が持っているリストには、逆にリックの名前が書かれているかもしれない。
ガーランドはリックが人間であるポロコフを殺してしまったのではと睨んでいたが(フィル・レッシュがいたのでそう振る舞っていた?)、脊髄検査の結果、ポロコフは人間型ロボットだったことが判明した(脊髄検査であれば100%見分けられるとされている)。
これでリック側の主張が正しいと観念したようだ。
それでもなお強気の態度を取るフィル・レッシュに、ガーランド警視はいらつき、呆れている様子だった。
フィル・レッシュは自分が人間で、上司のガーランドのことをアンドロイドだと疑っているようだ。
ガーランド、レッシュ、リックの3人は互いにテストを行うことに同意する。
<11> ミッション通り司法本部
フィル・レッシュが検査器具を取りに外へ出ると、ガーランド警視は自分自身もフィル・レッシュもアンドロイドであることを告白する。
フィル・レッシュの態度は気に食わなかったが、署員の士気に影響するという名目でテストは避けてきたのだ。
先ほどリックが映話したときに家内に繋がらなかったのは、この建物内で細工されているかららしい。
リックのリストに載っている名前は、すべてガーランドが知っている名前であり、いっしょに火星から逃れてきたアンドロイドたちだった。
ここで、リックとガーランドの認識は次のように一致する。
- ガーランド警視 … アンドロイド(火星から脱走)
- フィル・レッシュ(バウンティ・ハンター) … アンドロイド(火星から脱走)
- リック(バウンティ・ハンター) … 人間 or アンドロイド
ガーランドは検査器具を持ってきたフィル・レッシュに銃口を向けたが、逆に頭を撃ち抜かれてしまう。
フィル・レッシュはリックに、すぐに劇場のルーバ・ラフトを始末しに行こうと提案する。
バウンティ・ハンターのリックに対して仲間意識を持ち始めているようだ。
リックはフィル・レッシュに真相を伝えるべきか葛藤する。
自分たちが破壊しようと誓った対象は、きみ自身なのだと。
劇場への道中で、フィル・レッシュは本物のリスを飼っているのだと語る。
生き物に対する愛情を持っており、毎日世話をしているのだと。
でも自分自身が本当に人間なのか、はっきりさせたいとも考え始めていた。
<12> リック&フィル・レッシュ @オペラ劇場
オペラ劇場に着いたバウンティ・ハンターの2人は、ミス・ラフトは仕事を終えて美術館に行ったと知らされる。
もう逃げてしまったのかと思ったが、ルーバ・ラフトは実際に美術館で絵画を鑑賞しており、2人に見つかると血の気が引いた表情をした。
彼女は自分が火星からの脱走アンドロイドだと認識していたが、ずっと人間と同じ思考や行動をするように振る舞ってきたのだ。
彼女はその美しい歌声で人々に感動すら与えている。
まずはラフトを連れ出して検査にかけるつもりだったが、彼女に罵られたレッシュが撃ち殺してしまう。
若い女性であるラフトを始末した後に何の感情も示さないレッシュを見て、リックは「冷たいやつだ、アンドロイドに違いない」と確信する。
屋上のホバー・カーに戻ると、リックはレッシュを検査にかけた。
驚くことに、その結果は人間であると告げていた。
リックは動揺していた。
機械のような冷たさを感じたフィル・レッシュは人間だった。
人間に感動を与え、自分自身も感情を持っているように振る舞っているルーバ・ラフトはアンドロイドだった。
これは何だ?
自分はルーバ・ラフトのことを生き物だと感じた。
これはアンドロイドへの感情移入なのだろうか?
これは何を意味しているのか?
<13> イジドアとプリス・ストラットン
家路に向かうイジドアは、食料とワインをたずさえていた。
プリス・ストラットンと夕食をするためだ。
プリスはそれを見ると一瞬歓喜の表情を浮かべたが、すぐに苦渋の顔に変わった。
自分はバウンティ・ハンターに狙われているのだと打ち明けたが、イジドアには何のことかわからない。
一般大衆には地球にそういったアンドロイドが紛れていることは知らされていないのだ。
イジドアは、この娘は灰で頭をやられて被害妄想に悩まされているんだと思う。
食事を摂るプリスは、自分の生まれや火星のことを語り始める。
7人の知り合い(ポロコフ、ガーランド、ルーバなど)がいたが、もうバウンティ・ハンターにやられているかもしれないのだと。
そのとき玄関のドアにノックの音が響き、プリスの知り合いのロイ(男)とアームガード(女)だと名乗る声が聞こえた。
<14> ベイティー夫妻
プリスは、残ったのが我々3人だけだと知らされる。
ベイティー夫妻(ロイ&アームガード) も、バウンティ・ハンターから逃れるために、このおんぼろビルにやってきたらしい。
うわべでは興奮しているように見えるが、イジドアには彼女らが奇妙な思考をしていることを感じ取っていた。
ベイティー夫妻はプリスとイジドアに一緒に暮らすよう提案し、プリスはそれに従うことにした。
ロイ・ベイティーが 8 人のリーダーであり、火星から地球までの旅行を手配したらしい。
イジドアは、この 3 人が狙われているのはきっと何かやってしまったからだと思う一方で、バウンティ・ハンターなる者が人の命を狙うなんてひどいとも思う。
ロイはイジドアの部屋に人間の接近を警告する装置を仕掛けるが、その際に口を滑らせてイジドアに自分たちがアンドロイドであることがバレてしまう。
しかしイジドアは自分がマル特と見なされ火星に行けない立場であるため、彼らのことを同じような境遇の仲間であると感じていた。
<15> リック・デッカード @自宅
リック・デッカードはアンドロイド 3 体を仕留めた懸賞金の 3000 ドルを頭金にして、本物の山羊を購入した。
ローンの金額は大きかったが、自分自身の正体に対する自信を取り戻さなければならなかった。
妻のイーランは屋上の山羊を見るととても喜び、共感ボックスでこの気持ちを世界中のみんなと分かち合うべきだと言う。
2 人が部屋に戻ると、上司のブライアント警視から映話が入り、今夜中に残りの 3 人を仕留めろと命令されたが、リックは自分には処理しきれないことが分かっていた。
リックはローゼン教会にダイヤルし、アンドロイドのレイチェル・ローゼンに助けを求めることにした。
リックはレイチェルをサンフランシスコのホテルに誘い、彼女はそれに応じる。
<16> リック&レイチェル @セント・フランシス・ホテル
ホテルに到着したレイチェルに、リックは残りの 3 人のアンドロイドに関するメモを見せた。
レイチェルは、その中のプリス・ストラットンのメモを見てひどく動揺した。
そのネクサス6型は、レイチェルと同じ種類であり、見た目が非常に似ているのだと言う。
レイチェルはプリスとの妙な一体感を感じてしまっていた。
自分が処理されても別の個体が引き継ぐだけなのだ。
自分という存在があるのはただの幻想にすぎなかったのか?
レイチェルは、自分と寝てくれたらプリス・ストラットンを始末してあげると約束した。
<17> リック&レイチェル @3人のアンドロイドの元へ向かう車内
リックはもう自分はバウンティ・ハンターとしてはおしまいだと感じていた。
もう二度とアンドロイド狩りはできないだろう。
レイチェルは自分と寝たバウンティ・ハンターはみんな感じになったと言った。
ただ一人、フィル・レッシュを除いては。
それを聞いたリックは麻痺した気分になった。
レイチェルは教会はいつもこの手を使うのだと言う。
自分はいままでに 9 回同じことをしたのだと。
突然リックは彼女を殺すことにしたと言い出し、レイチェルも諦めて受け入れた感情のようなものを見せたが、結局リックは手を出すことができなかった。
レイチェルに再び自信が戻っていた。
リックにはもうアンドロイドを殺せない。
彼女だけではなく、ベイティー夫妻も、ストラットンも。
レイチェル・ローゼンは勝利を確信していた。
<18> バスター・フレンドリーの重大発表
バスター・フレンドリーが今夜重大な発表をすることになっていた。
イジドアがテレビをつけると、バスターは「マーサー教はイカサマであると」発表した。
マーサーなど存在せず役者が演じているだけで、共感ボックスによる人間の感情移入の全体験がイカサマだったのだと。
バスターはアンドロイドだった。
イジドアの心の中で何かが崩れ、まわりで崩壊が始まった。
気がつくと共感ボックスを握っていた。
<19> 脱走アンドロイドの最後
イジドアの部屋の警報ベルが鳴り響いた。
バウンティ・ハンターが来たらしい。
リック・デッカードは、ビルの外に出てきたイジドアに部屋への案内を頼んだが、イジドアは応じない。
リックがビルに入ると、目の前にマーサーが現れて危険を知らせてくれた。
背後を振り向くとレイチェルとそっくりなアンドロイドが近づいてきたが、リックは彼女を撃つことができた。
リックはイジドアの部屋を見つけると、残りのベイティ夫妻を片付けた。
ロイ・ベイティーは妻のアームガードが撃たれたとき悲痛な叫びを上げ、自分が息絶えるときにも断末魔を上げたが、リックはその 2 人に目もくれず何の感情も示さなかった。
後から入ってきたイジドアは泣いていた。
<20> 帰宅
ハリィ・ブライアント警視に報告を終えたリックが帰宅すると、妻のイーランが取り乱していた。
屋上で飼っていた山羊が若い女に殺されたのだと言う。
レイチェルがわざと妻に姿を見せたのは、アンドロイドなりの理由があったのだろう。
リックは一人、北にある無人の荒野を目指していた。
自分に死期がせまったことを感じていた。
<21> 影法師
なんて奇妙な場所を死に場所に選んだのだろうとリックは思った。
灰色の山腹を登り始めると、石ころがぶつけられた。
前方を見ると、マーサーの影法師のような姿を見た。
マーサーは俺だ!
ここにいちゃだめだ!
リックは何とか山を下り、車から妻に映話をかけようとした。
<22> エピローグ
リックは車の近くに絶滅種のヒキガエルを見つけた。
マーサーにとっての神聖な動物とされており、何百万ドルもの賞金がかけられている。
家に持ち帰ってイーランを驚かせてやろう。
家に着いたリックは子供のような笑顔を浮かべていた。
イーランとヒキガエルを眺めていると、腹の部分に制御パネルを見つけ、リックは心底がっかりした。